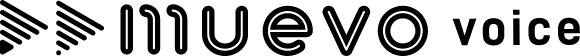日本の総人口1億2711万人に対して、1億9569万件。なんの数字だか、お分かりだろうか。国内における、携帯電話の契約数だ。現在、普及率は150%以上になる。僕の知り合いにも、ケータイを持っていない人は、一人しかいない。
先日、新宿の喫茶店で、ひとつ前の原稿を書いていたときのことだ。その店は地下に行くほど広がっていて、僕の席から、階下を見下ろせる。プールのように広い店だ。少し書き疲れたので、僕は小休止をとることにした。首を回した際に、下のフロアが目に入った。
フロアにいる全員が、スマートフォンを触っていた。目の前の人と話さずに、遠くの誰かとSNSで、話しているのだろうか。スマホ依存が問題視されているが、たしかに、距離をとって見てみると、不気味な光景だった。なかには、誰かが話しかけているのに、スマホに夢中の人もいた。
外で、イヤホンマイクを使って電話をしている人を、たまに見かける。いまだに僕は、ビックリしてしまう。シンプルに、見た目が怖いのだ。独り言にしか見えない様相で、大笑いしながら、中空に向かって話すさまが怖い。人の様子を見ると、僕もスマホ依存気味な気がして、気をつけたくなった。もはや、スマホを使わないわけにもいかないが、人間あってのスマホだ。
良いか悪いかは置いておいて、スマホは僕たちの生活を支えている。これは、紛れもない事実だ。人生レベルで、現代人に欠かせなくなっていると、言ってもいい。
それにしても、みんながみんな、Apple社のスマートフォンを使っている。僕もずっとiPhoneだけど、これほど一つの会社が、ケータイ市場のシェアを独占したのは初めてだ。現在、日本のiPhone普及率は30%前後。これは、世界一の数値だ。生産国のアメリカより上なのだ。
だが、むかしから、こうだったわけではない。僕が携帯電話に触れだした頃は、もっと各会社がしのぎを削っていた。言うならば、ケータイ戦国時代だった。NEC、パナソニック、シャープの三強に、東芝、ソニー、三菱、三洋、富士通が続いた。現在と比べると、当時のシェア率は各社、似たり寄ったりで、すべての会社が、品質改善に精力的だった。
そして、シーンの中心は国産だった。iモード、カメラ付き、音楽、ワンセグ、オサイフケータイ、写メール、着メロ。日本独自の「技術」と「文化」で、市場はにぎわっていた。「軽量小型化技術」と「合体文化」だ。
胃カメラや、乾電池は「小型化」の最たるものだ。CD(コンパクトディスク)も、カッターナイフも、じつは、発明したのは日本人だ。鉛筆のおしりに消しゴムを付けたり、ウォシュレット(トイレ+シャワー)や、テレビデオ(テレビ+ビデオ)、ラジカセ(ラジオ+カセット)。これらは「合体文化」による日本人の発明だ。
日本の「ものづくり」は「すでにあるもの」を小さくしたり、掛け合わせることで、この世に無いものを作り出してきた。日本の技術屋の特性と、ケータイの相性は抜群だった。
カメラ搭載、着メロ、写メールはすべて、世界初の技術だった。製作難度が極めて高い、スライド式ケータイや、超薄型ケータイなど、次々と新しいケータイが生まれた。これらは、日本の技術の高さを持ってしか、作れなかった。ちなみに、iPodの背面の鏡面加工は、新潟県で行われていた。あのスティーブ・ジョブズも、日本の技術の高さには、舌を巻いたのだ。
国外のスマホがメインとなり、「日本のケータイ」はガラパゴス、ガラケーなどと言われるようになった。しかし、「日本のケータイ」は、凄いのだ。イマ一度書いておきたかった。
そして、僕が初めてケータイを手にした2003年は、「日本国民、総ケータイ時代」の足音が鳴り始めた、発展期だった。「カメラ付きケータイ」が市場を占め、J-PHONE(ジェイフォン)はVodafone(ボーダフォン)と、社名を改めた。ケータイの普及率は、90%を超えた。1993年の3.2%を考えると、驚異的な進捗だ。
僕が一番最初に手にした機種は「P504iS(ピー・ゴーマルヨンアイエス)」という、パナソニックのケータイだった。当時はまだ珍しかった、インカメラを搭載していた。液晶画面がとてつもなく薄かった。2cm以下だった。この「P504iS」を手にしたとき、高校一年生だった。今と違い、ケータイは「子どもが触るもの」ではなかった。もちろん、セキュリティなども無かった。
だから16歳になる年、大人の仲間入りをした第一歩として、買ってもらえる家庭が多かった。ほとんどが、高校の入学祝いだった。
その頃、初めての彼女ができ、一日に何通もメールをやりとりした。今のようにLINEやSNSなどなかった。スタンプやリツイートも無かった。華やかさでは、スマホ全盛時代と比べると、足もとにも及ばない時代だった。それでも、スマホの半分ぐらいしかない小さな画面には、僕らなりの小さな世界があった。
幼稚園の頃、秘密基地を作った感覚だった。子どもだけしかいない閉鎖空間は、いくつになっても、僕らをワクワクさせた。ケータイによる電脳世界は、親や教師、大人たちの監視下から離れた、ひとつのシンボルだった。
僕らは、秘密を「携帯」し、思想を「携帯」し、ロマンを「携帯」した。ケータイには、家の固定電話では、決して味わえない「自立」が凝縮されていた。僕らは大人の手を離れ、小さな世界だけで通じる、僕らだけの言葉を手に入れた。
ケータイの進化は、あまりにも早い。早すぎる。たかだか13年前の出来事を書いただけで、現在とのギャップに目がくらむ。
今、この文章を読んでくれている、あなたの手にも、スマホが握られていると思う。15年後、2031年には、どんなケータイライフが待っているのだろうか。ケータイは存在しているのだろうか。
文・平井拓郎

QOOLAND