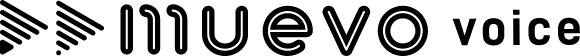土手の向こうから音がした。風がススキを鳴らす音だった。草木の音が無いと、その存在に気づかないぐらい、ささやかな風だった。
土手に上がってみた。見下ろす淀川に夕焼けが反射して、キラキラ光っていた。左手首の時計は、もう17時を指していた。
ススキが歌っているみたいな音が、重なって聴こえてくる。川の向こう側のスカイビルは、真っ赤に燃えていた。ここから見えるすべてが綺麗で、ここに来る前に起きたすべてが、汚らわしく感じた。
「あの子、いつ辞めるんかな!?」
裏の休憩室から、店長の声が聞こえた。他のバイトの笑い声もする。また、僕のことを言っているのだと思った。レジに立っている僕に、聞こえないはずがない。大声で耳に刺さる悪口が、めんどくさかった。
コンビニのバイトを始めて、もう2週間も経つ。それなのに、僕は全然慣れなかった。つらい。バイトのつらさが、永遠のように感じていた。バイトに行く前はいつも、死にたくなった。
簡単なレジ打ちはできるようになった。だけど、それより上の仕事が、ほとんどできなかった。
宅配サービスがどういうシステムなのか、まったく理解できなかった。公共料金の支払いや、切手の売り方、チケットの受け取りも、よく分からなかった。商品の補充もできなかった。
教えてくれる店長や先輩は、物覚えの悪い僕に対する態度が、だんだんと変わってきた。僕は典型的な「ダメ店員」だった。しかし、これまでバイトの面接を7つ連続で落ちてきた。生活費も底をついた。辞めたいけど、この店を辞めるわけにはいかなかった。
「……おい! おい、ライト!」
声がして、ハッとした。気がつくと、中年の男がレジに並んでいる。
「す、すみません」。反射的に僕は謝った。
「ライト!」。男は繰り返した。
男は、デスノートの主人公の名前を叫び続けている。ワケが分からなかった。ライトって一体なんだ。
「マイセンのライトや!はよせぇ!」
「かしこまりました。すみません……」
〈タバコなら、タバコって言えよ〉
イライラしている男に、マイルドセブンのライトを渡す。ため息が出た。早く帰りたかった。時給は720円だった。
22時になった。ようやく帰れる。この空間から一刻も早く消滅したかった。帰ってギターを弾きたかった。なんだか猛烈に、音楽に触れたくなっていた。音楽で、この気持ち悪さをかき消したかった。
ただ、帰る前にやることがある。店長にお願いがあった。僕は、深夜帯に働こうと思ったのだ。昼はお客さんが多くて、嫌だった。昼の先輩たちも嫌いだった。夜勤で、生活が逆転するのはつらいけど、昼の苦痛よりはマシだと思った。帰り際、店長に相談した。
「夜勤にしてもらえますか?」
店長はイスに踏ん反りかえって、ケータイをいじっていた。そして、僕を見もしないで言った。
「お前、面接で昼に入るって言ってたやろ。なんなん?」
「なんなん」と言われても、答えられない。「昼がしんどいから」とも言えない。適当なウソも思いつかない。僕が黙っていると、彼は口を開いた。
「もうええわ。じゃあ来週から、塚本の店舗で夜勤な」
塚本というのは、隣り町の名前だ。店長は店舗をふたつ持っていた。僕の家から塚本は、自転車で10分とかからない。塚本のコンビニは通り沿いにあるせいで、昼はずいぶんと忙しそうだった。
夜勤は先輩と2人体制になる。交互に休憩して、1人ずつ店番を行う。夜勤初体験の日、僕のパートナーは、田岡さんという先輩だった。
「ふつう1時間ごとに休憩するけど、めんどいからまとめて2時間ごとな」
田岡さんは、めんどくさそうに言った。夜勤は22時から、朝の7時まで働く。本来は1時間ごとの休憩だが、田岡さんは自分でシステムを作りかえていた。
まず、僕が休憩することになった。出勤して、いきなり深夜0時までヒマになってしまった。「これなら、0時にタイムカードを押せばいいんじゃないか」と思った。
夜勤は圧倒的に楽だった。起きているのはつらいが、嫌な店長や先輩もいないし、お客さんも少ない。田岡さんと特別、仲が良かったわけではないが、そもそも交代制なので、仲良くする必要もなかった。と書くほど、長く働いてもいないのだが。
なぜなら僕は、夜勤を3日間しかできなかった。
4日目の出勤日の夕方、僕は店長に呼び出された。昼に働いていた店舗に行くのは、久しぶりだった。店長の顔を見たのも久しぶりだった。相変わらず、イライラした表情をしている人だと思った。
僕を見るやいなや、店長は口を開いた。
「お前、2時間おきに休憩してるらしいな?」
急な質問に、僕は動揺した。
「え? はい。田岡さんにそう言われて、してます」
「じゃあお前、田岡が『人殺せ』言うたら殺すんか!」
意味が分からなかった。分からないが、どうやら田岡さんの考案した、2時間ごとの休憩が違反だということが、ジワジワと分かってきた。店長は僕が2時間ごとに休憩していることが、どうしても許せないようだった。
「おい、みんな聞いたか!? コイツ勝手に休憩変えて、『田岡さんに言われて』とか言ってんぞ!」
お客さんはいなかったが、昼のバイトの人たちが大勢いた。みんなが僕を白い目で見ていた。少しずつ、笑い声が起こりだした。胃が握り込まれたみたいに気持ち悪くなった。食べたものが出てきそうだった。生活費のことなど、頭から消えていた。とにかく、ここから立ち去りたかった。
「すみません。辞めます」と、目も合わせないで告げた。
「おう、辞めてくれ」
怖いぐらい自然な「辞めてくれ」だった。人が一人、退職するというのに、極めて日常的で、ふつうで、業務的だった。ゴミ捨てや掃除業務のように、日常のなかの、流れのひとつとして、僕の退職は扱われた。
コンビニを出て、一目散に走った。この場所から、少しでも遠い場所に行きたかった。物理的に遠い場所でも、本質的に、心情的に遠い場所でもいい。とにかく、遠くに行きたかった。
走っている途中に、また気持ち悪くなって、電信柱のわきで吐いた。通行人の視線が気になる。悲しくなった。悲しくて、たまらなかった。少しの怒りも感じていた。でもその混じった感情が、誰のせいか、何のせいかなのかは、分からなかった。コンビニの仕事ひとつできない自分に対してなのか、店長に対してなのか、他のバイトに対してなのか。
これからの予定も、何もなくなった。川を見に行きたくなった。近所にある淀川が大好きだった。淀川を見ていると、嫌なことが、かすんでいく感覚がした。
川は、ひたすらとめどなくて、綺麗だった。朝焼けも夕焼けも、昼の風景も、夜の月も。淀川は、どんなときも美しかった。僕の身のまわりの嫌なことから、川はとても遠い場所だった。
川を見て、じっとしていた。じっとしていると少し寒かったが、その寒さも心地よかった。ススキが吹かれる音と、川の流れる音を聞いているうちに、落ち着いてきた。
つらいことも、いつかは流れていく。あらゆるものは少しずつ流れて、見えなくなっていく。淀川は、僕を励ますように、ただ流れていた。働けなくなったことも、明日からの生活費も、大した問題じゃない気がしてきた。陽はすっかり傾いていた。気付くとスカイビルから、燃えるような色が消えていた。
文・平井拓郎

QOOLAND